ワンダーランドのベルを鳴らして
「最近の女学生のスカートは凝っているな」
そう思わないか、川端。そう言いながら、鏡の前でターンする様に振り返ると、横光の着ている、上品な濃灰色のセーラーカラーと、慎ましやかなボックスプリーツの裾が、膝上をかすめながら、踊るように翻った。
「ええ、確かに」
微かに笑って同意する有人もまた、横光と同じセーラーのツーピースを身につけている。メイクと称して差した、薄い薔薇色のリップクリームのおかげか、いつもより血色が良く見えるようだ。
昨日まで男だった新感覚派の二人が、何故か今朝から女になった。
稼働して一年目やそこらの図書館なら大騒ぎになるところだが、稼働してから、はや三年以上が経過したこの図書館では、この手の騒動は大概発生済みだ。やれ潜書から戻ったら子供になっただの、怪しげな薬を飲んだら猫耳が生えただの、数え上げれば枚挙に暇がない。
大多数の人間が――当の本人達すら、暢気に静観を決め込むうち、どうせなら写真を残しておこう、という声がどこからか上がった。事の面白さを嗅ぎつけた文士や、服飾に一家言ある文士などがぞくぞくと集まり、正午を迎える頃には、衣装をベースとした新しい錬金術の検討に、という司書と師匠も加わって、いつの間にやら新技術検討会という名の、着せかえ撮影会が催される運びとなった。
「慣れてきましたね、利一」
「まあ、これだけ着ればな」
茶化すような友人の微笑みに、横光は苦笑いを返しながら頷いた。
物置を即席の更衣室に、談話室を撮影スタジオにして、昼から続けてきた遊びも、そろそろ終盤だろう。引かれたカーテンの隙間から差し込む光は、淡い夕日の色だ。柔らかな茜色が、セーラー服の白いブラウスに、ほのかな彩りを添えている。その様子を眺めつつ、横光は用意された姿見を覗いた。
鏡に映る横光と川端の制服姿は、髪型や互いの雰囲気も相まって、一見双子のように見える。唯一の違いは靴下で、川端は三つ折りの白、横光の方は紺のハイソックスだ。流行のブラウス、フリルの多用されたジャンパースカート、清楚なワンピース、女学生の制服など諸々着てきたが、用意された衣装もあと一着。毒食らわば皿までか、と横光は用意された紙袋に手を伸ばした。
「・・・・・・」
手に取った最後の衣装は布量が少なく小物が多い。簡単なビニール袋で小分けされたそれを取り出して、はた、と気がつく。
「川端・・・・・・」
おそるおそる声をかけると、同じく衣装を紙袋から取り出した友人も、その衣装がどんなものか気付いたようだ。動きを止めて、ふむ、と首を傾げて考える素振りをしている。
取り出した一着は、肩布のないレオタードと、それに合わせるストッキング。小物として小分けされた透明のビニール袋には、付け襟とネクタイ、カフスが揃えられ、極めつけにウサギの耳を模した髪飾りがセットになっていた。横光は話でしか知らないが、これは所謂バニーガールと言うものだろう。
「これは・・・・・・悪ふざけが過ぎるな」
思わず眉間に皺が寄った。ワンピースや制服あたりなら、まだ遊びの許容範囲だが、エロティシズムを強調した衣装となれば話は別だ。ビニール袋の中のウサギ耳は先が折られていて、どちらかと言えば愛らしさをアピールしているようだが、そんなものは何の救いにもならない。
「少し、抗議してくる」
「まって下さい、利一」
踵を返し、鏡に背を向けた横光の片腕を川端が掴み、その場に押しとどめた。
「川端?」
「・・・・・・」
川端はそのまま横光の正面に回り込む。勢いに押されて、数歩後ずさった横光の背中が、背後の姿見に軽くぶつかった。友人のいつにない素早い行動に、目をしばたかせていると、川端の右手が彼のセーラーカラーの中心に向かう。同時にしゅるり、と彼の胸元からスカーフが解かれる音がした。
「どうした川端?」
「利一」
薄幸そうな美少女が、こちらに向かってにっこり微笑む、という構図を嫌いな人間はそういないだろう。しかし、いかんせん目の前で微笑んでいるこの少女は元男で、こちらも元男の現在見た目は少女である。これの何処に需要があるというのか――いや、図書館の一部文士や司書には垂涎ものかもしれないが。そういえば司書の愛読書は、吉屋女史の花物語だと以前聞いたことがある。さもありなん、それでこの企画の力の入れようか。
埒もないことを考えている間に、川端によって横光のスカーフも胸元の結び目が解かれている。友人の手が、そのまま横光の前あきスナップを外し、セーラーカラーのブラウスが肩から滑り落ちた。
「せっかくここまで着たのですから……はい、バンザイ――着てみるのも良いじゃありませんか」
「だとしても――ん――さすがにこれは」
つられて思わず両手をあげたところで、丈の短いシミーズ――きゃみそーる、というらしい。が頭の上から引き抜かれる。
「それに・・・・・・菊池さんが用意してくれたものですよ」
言いながら、友人は手際よく自身の上着とシミーズを脱いで、無造作に床の上に落とした。足元でもつれ合う、二着のセーラーカラーに妙な背徳感を覚えて、横光は思わず視線を逸らす。
「本物、見せてあげたくないですか?」
「――その説得は卑怯だ・・・・・・」
日本でバニーガールという接客形態の店が広がったのは、横光と菊池が世を去ってからだ。知識や伝聞、映像として知ってはいても、二人は実際のバニーガールを見たことがない。それに、と川端は笑う。
「貴方、ひとりでホック留められないでしょう」
「む・・・・・・」
いつの間にやら、下着のホックが外されている。着付けの時にもさんざん手間取り、結局友人に留めてもらったのだ、横光ひとりでの原状回復は難しい。
ちなみにその最中、やっぱりフロントホックにしますか、いや何となれば俺が毎朝やってやるから、最近はフロントホックも可愛いのありますよ。という司書と師匠の、妙に楽しそうな会話が漏れ聞こえていたのは、まあ聞かなかった事にしてある。
「掏摸顔負けの特技だな」
「貴方以外に使いませんから、大丈夫ですよ」
「どういう理屈だ・・・・・・というか、川端も同じものを着るんだぞ」
最後の悪足掻きとして、苦し紛れに問いかけると、やや間を置いて、意外なほど真剣な声が返ってきた。
「・・・・・・まあ、私も男ですから、多少の抵抗は感じますが」
利一の可愛らしい姿を一番に見られて私は眼福ですよ。と眼前で下着姿の美少女――七十二歳まで生き、世界的にも有名な作家であった男は、大変男前な甘い台詞を言いながら、それは幸福そうに笑う。
「――それに、肉を切らせて骨を断つ、といいます」
「何か違うと思うが……」
がっくりと肩を落としたところで、入り口の扉をノックする音が耳に届く。焦れた師匠か、手伝いの名目で出歯亀を目論む司書だろうか。
視界に映る、友人の手にしたウサギ耳のカチューシャと、逃げ場のない状況。横光の脳裏に、どこかの作家の書いた、不条理ナンセンス小説の情景が目に浮かんだ。
「本当に、新感覚だな」
「ええ、悪くないでしょう?」
ふふ、と数十年来の盟友に、心の底の僅かな享楽を見抜かれてしまえば、最早ぐうの音も出ない。
乗りかかった船、騎虎の勢い、尾を踏まば頭まで。横光は腹をくくって、スカートのファスナーを開け、川端は自分の下着のホックを外す。
濃灰色のスカートが、空気を含んだ衣擦れの音を立て床に落ちるのと、二対の淡い薔薇色のリップクリームが重なるのは、ほとんど同時だった。
書いてる途中に新感覚の指環が届いたので、必要以上にいちゃつかせてしまった。
というか、あいかわらず二人にした途端にいちゃつき出すのやめてください。
当初はもっと軽いギャグ寄りのプロットだったんだよ…
ネタ元は、百合メーカーさん(https://picrew.me/image_maker/59568)
で作ったそれっぽい子達↓。
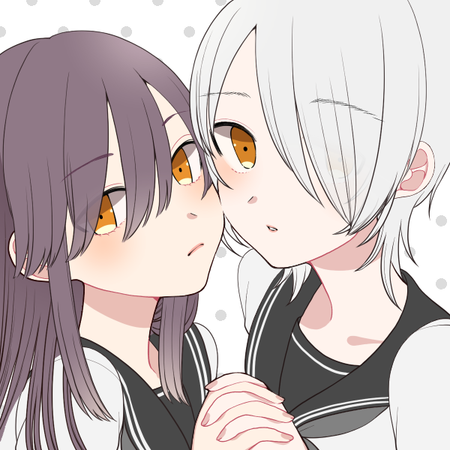


我ながらそれっぽく可愛い子ができたと思う
可愛い…